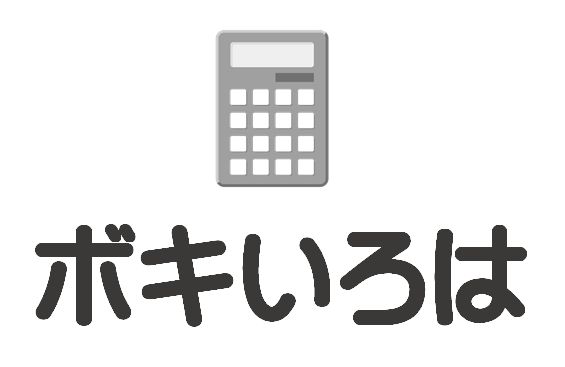日商簿記2級ってどんな資格なの?
日商簿記2級は、転職サイト等が実施する「企業が求める資格ランキング」においても堂々の1位になるなど就職や転職にとても有利な資格です。
また、多くの大学の商業科・経済学科などの推薦入試の基準となっており、推薦入試にも使える資格となっています。このように、多くの場面で活躍してくれる素晴らしい資格といえます。
なお、日商簿記2級は、3級で学習する「商業簿記」に加え「工業簿記」という科目が加わることになります。つまり、「商品販売業」の簿記の知識に加え、「製造業(メーカー)」についての学習をしていくことになるため、幅広い業種の知識を得ることが出来ます。
商業簿記と工業簿記の違いについて
<商業簿記>
完成している商品を仕入れて売る会社(商品販売業)の記帳方法
<工業簿記>
材料を仕入れて製造したものを製品として売る会社(製造業)の記帳方法
日商簿記2級のレベルについて
日商簿記2級のレベルについて、検定主催者の日本商工会議所は下記のように記載しています。
経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ。高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理や分析を行うために求められるレベル。
日本商工会議所HPより
簡単にいうと、「高度な商業簿記の知識と工業簿記の知識を得られるため、幅広い業種での適切な会計処理・分析が行えるレベル」となります。3級のレベルには、「分析」という文言が出てきておらず、この点からも2級のレベルの高さが伺えると思います。
2級の合格率は20%程度なので難易度はかなり高いです。また、2019年度の試験から試験範囲の改正が行われ、これまで1級の範囲だった内容が2級の範囲となったり、一段と範囲が広くなっています。
ただ、今回改正された内容は、「リース取引」や「外貨建取引」など実務においても役立つ項目が多く、学習すべきものばかりです。
なお、「学習のしやすさ」を考えると未知の学問を学ぶ3級よりも2級の方が学習しやすいのは間違いありません。試験範囲が広くなり、覚えることも多くなりますが、各項目を1つずつ理解する学習をしていけば、問題なくこなせる内容ばかりです。
3級とのダブル受験も可能
日商簿記2級と3級の試験時間は午前と午後で異なりますので、少しヘビーですがダブル受験も可能となっています。チャレンジできる方はぜひ2級と3級のダブル合格を目指してみましょう。
YouTubeチャンネルについて
当サイトでは「ボキいろは」という日商簿記の基礎を無料で学べるYouTubeチャンネルを運営しております。現在、制作できているのは工業簿記のみですが、ぜひご活用下さい。